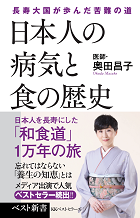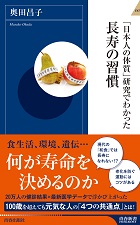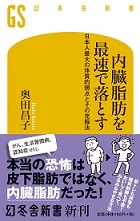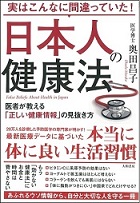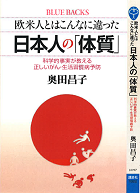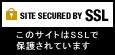「本を書く医師」が医学情報をわかりやすく伝えます

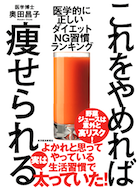
|
本を書く医師 Top |
満点がない仕事の進め方
|
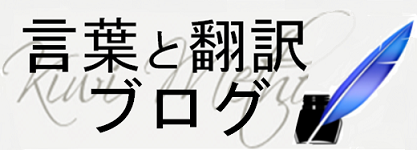
満点がない仕事の進め方
こんにちは。キーウィです。
本の原稿を2ヵ月ちょっとで書き終わり、ようやく出版社に送りました。毎度のことながら、納品前の一週間は、頭痛、めまい、耳鳴り、動悸、なんでもありで、心身の限界まで集中しているのがわかります。
知人に、「そんなに頑張らないと間に合わなさそうなの?」 と聞かれましたが、そういうわけではないんですね。いつでも送れる状態になっているのに、最終的な見直し段階に入ると欲が出てくるのです。「ここも見ておかないと」 「これも盛り込もうかな」 「この図は見栄えがいまいち」

さっと送ってしまえば楽なのでしょうが、職人気質というか、損な性格というか、手を入れることが楽しいのです。といっても、締め切りを守るのは基本中の基本なので、予定の締め切り日には 「行ってらっしゃい」 と送り出します。
くたくたになっても締め切りを守れるようにするには、最初からそのように予定を組んでおく必要があります。大切なのは、締切が迫ってからラストスパートするのではなく、スタートダッシュすることです。そうすると早い段階で全体像がわかり、不安なく進めていけます。
手順は執筆も翻訳も大差ありません。
① まず、ひたすら書きます(翻訳します)。最大のエネルギーを使ってバリバリ前進します。どうしても分からないとか、はっきりしないところは、判断を保留して印をつけておけばOK。ここで完成度5まで持って行きます。
② 書いていくと内容の理解が進むので、印をつけたところに戻って問題を解決します。改めて見ると、あまり重要ではないことがわかって、その部分を丸ごと削除することも。これで原稿の形ができあがります。完成度7というところ。① ②で、予定期間の半分くらい使います。
ここまでできていれば納期の心配はないでしょう。この逆に、中間地点まで来てもできあがっていなかったら厳しいですね。仕事自体の難易度が高いか、納期が甘すぎたかどちらかです。その場合は、納期を延長してもらう可能性について、早めに相談する必要があるかもしれません。

③ ここからは完成度を高める作業です。PC画面上で頭から推敲していきます。既に全体像が見えているので、原稿全体の整合性を取って、矛盾がないようにします。章単位で大幅に書き直すこともありますが、骨組みはできているので、文章や段落を並べ替える作業が中心です。(完成度8)
④ いよいよ職人の世界へ。原稿をすべて印刷し、赤ペンを片手に修正します。すでに何度か見直しているのに、気になるところがいくらでも出てきます。執筆だと、並行して参考文献をまとめ、図表を作成する必要もあります。原稿は大体できているので、心理的には余裕があります。
内容だけでなく、文章のリズムや流れにも目を配ることで、ぐっと読みやすくなるのがわかります。集中して読むので、駅で降りそこなったり、気がつくと、ぶつぶつ音読していたり。この段階で文章に魂が入るように感じます。(完成度9)
⑤ ここまでくると、提出期限まで1日か2日しかありません。図表や参考文献があれば、こちらも印刷して赤ペンで修正します。こうして原稿が揃っても、送信する最後の瞬間まで油断なく目を凝らし、気になることがあれば急いで修正します。(完成度9.5~)
上に書いた各段階の完成度は、あくまで主観ですが、最後までこだわりを持つことで、文章の質が格段に良くなるような気がします。荒削りだったものが、次第にこなれていくのを目の当たりにするのは達成感がありますね。文章に限らず、物作りの楽しさというのでしょうか。

これは有名作家も同じなようで、締切が近づくと腕が痛くて上がらないとか、ストレスで耳が一時的に聞こえなくなると書いているのを見たことがあります。こういう作業には満点がないので、「限られた時間の中で、どれだけ完成度を高められるか」がすべてです。