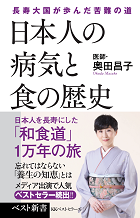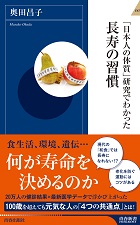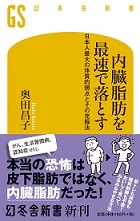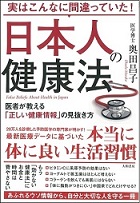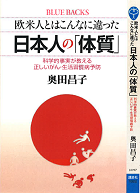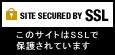「本を書く医師」が医学情報をわかりやすく伝えます

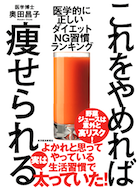
|
本を書く医師 Top |
納品前の最終確認をアナログで行う理由
|
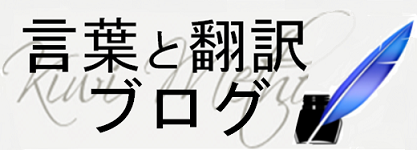
納品前の最終確認をアナログで行う理由
こんにちは。キーウィです。
読書が趣味という人に、iPad、Kindle、PC、普通の書籍で同じ小説を読んでもらって、所要時間と読書体験の満足度を比較する実験が行われました。すると、所要時間は普通の書籍が一番短く、iPad と Kindle が少し長くて、PCも大差ありませんでした。
その一方で読書体験の満足度については、 iPad と Kindle が普通の書籍より高かったのに対し、PCだけが飛び抜けて低かったそうです。画面が固定されているので読む側がPCに合わせなければならず、疲れるからではないかと分析されていました。

以前の記事に、納品前の最終確認の際は訳文を紙に印刷した状態で確認作業をしていると書きました。出版社などのプロの校正担当者も、印刷したものを専用の筆記具で一字一句、しるしを付けながら確認するそうです。
この理由は、PC画面だと簡単にスクロールできるために、しっかり確認する前にページを送ってしまうからです。
目が一つの情報を追っている時に、脳はその前に見ていた情報に関する照合作業をしていると言われており、何か気になることがあると直ぐ意識に働きかけて注意を促します。
「あれ? さっきのところ、何か変な気がする」 と思って見直したら本当に間違っていたので、慌てて書き直した、という経験はありませんか。
しかしPC画面では、この時点で既に画面が変わっているので、脳の注意を聞き流してしまうのではないかと考えられています。さらに、PCには画面が固定されている不自由さが加わります。
このように機能的にも心理的にも制約がかかることで、誤字脱字を発見するための脳のアンテナの感度が鈍ってしまうのです。

その意味では、iPad や Kindle のように手で持てる機器の方が効率よく人間の機能を補助してくれそうです。でも、光沢感や色調、画面のサイズ、動作性を含めて改良の余地は無限にあります。
人類は長い年月にわたって紙に文字や絵をかいてきました。紙に触れる音、触感、色の明暗、かすかなにおいは記憶と密接に結びついています。折ったり透かしたり重ねたりもできるのですから、紙自体が使われなくなることはないでしょう。
デジタル機器もデジタル技術の長所を活かすだけでなく、紙の利便性、快適性を再現する努力を続けてほしいと思います。