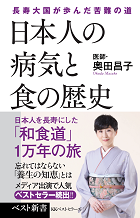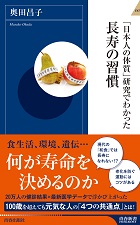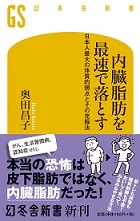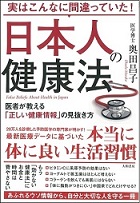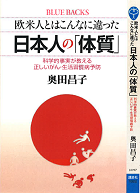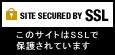「本を書く医師」が医学情報をわかりやすく伝えます

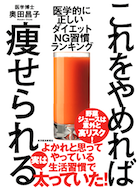
|
本を書く医師 Top |
文字のある文化と文字のない文化
|
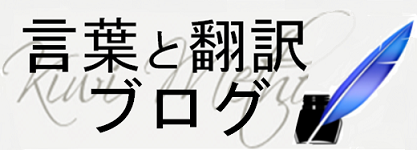
文字のある文化と文字のない文化
こんにちは。キーウィです。
雑談中に知人が 「文字ってインフラみたいなものだよねえ」 と言いました。「文字があるから文化とか伝わるわけでしょ。口でもいいんだけど、書いた方がみんなが読めるし、それをもとに考えたり何かを作ったりできるしね」。
こんな風に考えたことがなかったので面白いなあと思いました。一般にインフラ infrastructure と言えば、上下水道や道路などの社会基盤を指し、学校や病院などを含めて考えることもあります。

世界には、現在6500以上の言語が存在しますが、そのうち文字があるのは400ぐらいと言われ、文字のない言語の方が圧倒的に多いのです。身近な地域で言えば、ハワイ語も、台湾固有の台湾語も、アイヌ語も文字がありません。
日本語も同じで、漢字を導入するまでは知恵も知識も口伝えでした。古事記の編纂に関わった稗田阿礼の逸話が有名です。
話す言葉は一瞬で消え去る一方で、感情を揺すぶって記憶に残り、行動を促す力があります。人類は太古の昔から言葉が持つ力を知っており、生活の知恵や民族の歴史を物語にして、火のそばで世代から世代へ語り伝えてきました。
民謡を始めとする伝承音楽も同様です。北欧の北極圏で暮らすサーミの人たちの即興歌ヨイクは、今に受け継がれる美しい旋律です。
"Dawn Light 夜明けの光" (早朝飛来した白鳥に呼びかける美しい歌)

しかし、文字のない文化には負の側面もあります。知識の集積に限度があるうえに、口伝えで学ぶとなると、ごく少数の特権的な人しか知識を身につけることができません。大部分の人は知識にふれることができず、そのため良い仕事に就けず、貧困の悪循環に陥ることもあります。
また、他の地域の事例から学ぶことができないので、農業を近代化できずに食糧不足に苦しんだり、先進国ではとうの昔に制圧された感染症が今も猛威を振るっていたり、無理な妊娠出産により、無数の母子が日常的に死亡したりする地域もあります。
この現実を考えると、現代社会においては文字が社会を支えるインフラであることは間違いありません。やはり文字の普及が必要です。これに伴って伝統文化が破壊されてはなりませんが、文字を持って 1600年になる日本が古い文化を守ってきたことを考えれば、両者の両立は十分可能でしょう。